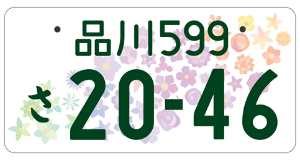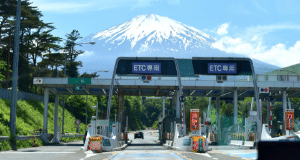パッシングは、ライトを点滅させることで、対向車などの周りに合図を送るために用意されている標準機能となっています。
以前は、色々な意味を持ってパッシングをすることがありましたが、最近ではあまり使われなくなってきています。
サンキューホーン(クラクション)、サンキューハザードなども同様ですが、威圧的な意味合いも含まれているため、無用なトラブルを避ける意味でも使用頻度は減ってきているのではないでしょうか?
ここでは、パッシングの正しいやり方やそもそもなぜ使われなくなっているのかについて、お話ししていきたいと思います。
パッシングの操作方法
まずは、パッシングの仕方についてですが、一般的にはライトスイッチのレバーを手前(運転手側)に倒すとパッシング、奥側(進行方向側)に倒すとハイビームになります。
ハイビームにする場合は、レバーが奥側で止まるものと、手を離すと中立位置に戻るものがありますが、パッシングの場合は手を離すと中立位置に戻るのが一般的です。
詳しい操作方法については、各車両の取扱説明書を確認してみて下さい。
パッシングをするシチュエーション
では、どんな場合にパッシングをするのでしょうか?
以前から、よく行われていたパターンを紹介していきたいと思います。
対向車に道を譲る場合(譲りたくない)
直進車両と右折車両がお互いに譲り合っている時に、「お先にどうぞ」という意味でパッシングをすることがあります。
道路交通法では、直進車両が優先なので本来は譲り合うことは無いのですが、細い小路などでは先に右折車両を行かせないと直進出来ない場面もあったりします。
そんな時には、パッシングして右折車両を促すこともありますが、最近ではハンドサイン(手で合図して)で促すことが多いと思います。
また、強引に右折してこようとする車両に対して、譲りたくない、直進車両優先であることをアピールする場合にもパッシングをしたりします。
歩行者に道を譲る場合
信号の無い横断歩道など、車両と歩行者が交差する場面では、歩行者が立ち止まってしまうことが多いですね。
後続車両が無かったり、急いでいない場合は、歩行者に道を譲る合図としてパッシングをすることがあります。
こちらも最近では、ハンドサイン(手で合図)で歩行者を促すことが多いと思います。
車線変更や合流地点で「入っていいよ」「入ってくんな」
車線変更や合流地点で、自分の前に車両が入ってくる場合に、「入っていいよ」という合図としてパッシングをすることがあります。
また逆に、強引に割り込もうとする車両に対しては、「入ってくんな」の合図としてパッシングする場合もあります。
どちらの意味でパッシングしているのか、分かりづらいため、最近ではこの用途で使われることはあまり無いと思います。
対向車や先行車に異変を知らせる
先行車両に対しては、「ブレーキランプが切れている」「トランク(ハッチバック)が開いている」「タイヤがパンクしている」などの異変を知らせるためにパッシングすることがあります。
また、対向車に対しては、「ヘッドライトが切れている」「ヘッドライトの無灯火、つけっぱなし」などを知らせるためにパッシングすることもあります。
お礼の意味
夜間の市街地、住宅街ではサンキューホーン(クラクション)は迷惑になってしまいます。
その代わりに、パッシングでお礼の合図を送ります。
追越車線をどけてくれ
高速道路で追越車線を走行中に後続車両からパッシングをされる場合があります。
急いでいるから道を譲ってくれという合図なのですが、最近では「あおり運転」と受け取られる可能性もあるので、余計なトラブル回避という意味でも、やらない方が良いかもしれません。
この先で検問やネズミ取りしている
対抗車両から、心当たりの無いパッシングがあった場合は、その先で検問やネズミ取りをしている可能性があります。
昔はよく、対向車が親切にそれをパッシングで知らせてくれていましたが、最近ではあまり見かけなくなってしまいました。
対向車がハイビームで眩しい
最近の車両は、ハイビームとロービームを自動で切り替えるモードが搭載されているので、少なくなっていますが、夜間走行中に対向車のヘッドライトがハイビームで眩しい時に、パッシングで知らせることがあります。
パッシングの正しい方法とは?
道路交通法では、パッシングの仕方について明確な規定を設けていないため、ドライバー同士の暗黙の了解として使われているということになります。
したがって、正しいパッシングの方法は無く、曖昧なものになっているので、パッシングした側の意図しない受け取り方をされてしまう危険性があります。
また、地域によっては、使われ方が違うこともあるので注意が必要です。
まとめ
サンキューホーン(クラクション)もそうですが、パッシングには、好意的な意味もありますが、警告の意味もあり、どちらにも受け取られてしまう可能性があるため、無用なトラブルに発展してしまう場合があります。
いずれにしても、今後はサンキューホーンもパッシングもしない方がいいかもしれませんね。